私の知らないおじいちゃんとおばあちゃん〜視覚障害者の祖父祖母について、父に聞く〜(楠本明日香)
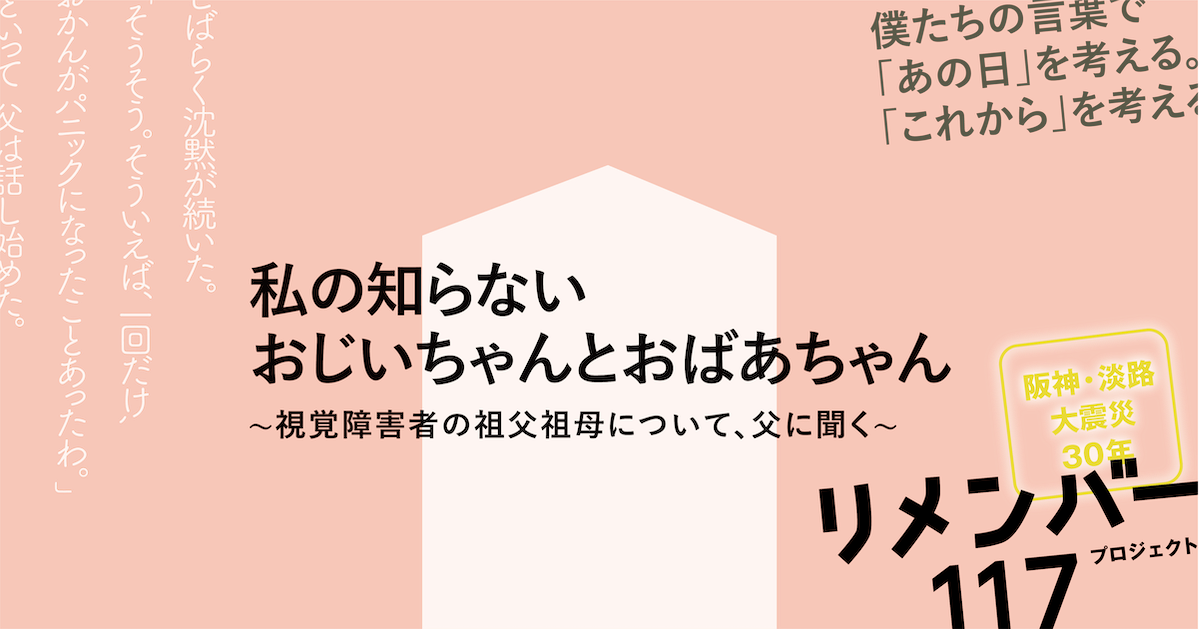
私は開けてはならない箱を開けるような思いで、父にあるメッセージを送った。
“おじいちゃんとおばあちゃんの話を聞かせて欲しい”
私が小学生の頃、父方の祖父母が視覚障害者ということを知った。おじいちゃんとおばあちゃんは、私の物心がつく前に亡くなってしまった。だから、私の記憶の中にいるおじいちゃんとおばあちゃんは、写真で見た、2人が並んでカメラに向かって微笑んでいる姿しかない。だが、それ以降、私は父におじいちゃんとおばあちゃんの話を聞こうとしなかったし、父も私に話そうとしなかった。
私の記憶にはおじいちゃんとおばあちゃんがほとんど残っていないが、大切な私のおじいちゃんとおばあちゃんに変わりはない。だから、私は視覚障害をもつ方に勝手ながら親近感を感じ、助けたいと思うことが多々ある。まずは、父におじいちゃんとおばあちゃんの話を聞いて、視覚障害者の生活や困っていることを少しでも知ろうと思った。だが、知るという行動を起こすには時間がかかった。知りたいと思う気持ちがある一方、父が今まで話さなかったのには何か理由があるのではないかと思い恐れる気持ちがあったからだ。私が、父にあのメッセージを送った1時間後、父から返信が来た。
“なんでも聞いてください ”
私は気持ちが高鳴るのを感じるとともに、自分が一歩先に進めた気がした。
そして、その週の休日の朝、父からビデオ電話がかかって来た。
「おはよう、最近どう?」
独り暮らしをしている私と単身赴任をしている父。他愛もない親子の会話が広がる。一通り近況報告を終えた私たちは、本題に入った。
私は、事の成り行きを父に話し、父に尋ねた。
「おじいちゃんとおばあちゃんと暮らしていた時、困ったこととか大変なこととかあった?」
父は18歳で親元を離れて暮らし始めたため、おじいちゃんとおばあちゃんと暮らしていたのはもう30年以上前のことになる。
父は顔をしかめながら、遠くを見た。父が何か昔のことを思い出す時の癖だ。しばらく沈黙が続いた。
「そうそう。そういえば、一回だけ、おかんがパニックになったことあったわ。」
といって、父は話し始めた。
ある日、おばあちゃんが家に1人でいて、普段通り生活していると、マンションの下の階が火事になってしまったそうだ。消防車の音、煙の匂い、炎の熱さを感じながらも、自分の周りが今どんな状況になっているか分からない。自分の身に危険が迫り来るっているのに、何も分からないし、できない。おばあちゃんはパニックになってしまったそうだ。五感のうちの一つ、視力を失うということは、どれだけ恐ろしいことなのか、私は身に染みて感じた。いくら自分が住んでいる家で慣れていたとしても、火事になると状況把握できず、1人で行動を起こすことなど不可能だ。私は父の話を聞きながら、情景を頭の中で思い描いていた。鳥肌がたった。父も私もおばあちゃんの気持ちを思うと、少しの間、口を開けなかった。
「あ!そういえば、物の置く場所が決まってたわ」
父は忘れかけていたものを思い出したように、そういった。私たち、視覚を持つ人たちは物を探すという行動を少なくとも1日1回はするだろう。しかし、視覚がない人たちにとって“探す”という行動は起こせない。ものを置く場所を決め、覚えておくしかない。例えに、テレビのリモコンを用いて、父は私に説明してくれた。‘’リモコンはテレビ台の上に置く‘’というように、1つ1つのものに置く場所が決められていたそうだ。その話を聞いて、私は納得したことがひとつあった。父は常に整理整頓をしてした。それは、私たち子供に“片付ける”ということを教えるというものではなく、ごく当たり前に。「雀百まで踊り忘れず」というように幼い頃の習慣が残っているのだろうと感じた。
そして、父は続けた。
「ひとつでもイレギュラーなことが起こってしまうと、それだけでパニックになってしまうんよ」
災害関連の仕事に就いている父は、地震が発生した状況ではどうなってしまうか教えてくれた。地震が起こり、家具が倒壊する。避難しようとしても、足元にどんな危険物が転がっているのか、白杖がどこにあるか分からず、すぐに行動を起こせない。さらに、普段助けてくれる人もイレギュラーなことに自分のことで精一杯になり、視覚障害者に手を差し伸べてくれる人は数少ない。実際、災害の被災地に足を運んだことがある父は、障害を持つ方たちの助けをする余裕はなかったと言っていた。
父との電話を切った後、私は父の話を聞きながら書いたメモを読み返した。
「おじいちゃんおばあちゃんのことやのに、自分ってなんも知らんかったんやな」
これが私のメモを読んだ時の第一に思った感想だった。そして、自分の親のことについて話す父の顔を初めて見ることができた。視覚障害者のことを知ることは、私にとって、私のおじいちゃんおばあちゃんについて知ること、私が見たことのない父の一面を見ることだった。知るという高かった壁を乗り越えた先にあった景色は、見たことのない私をワクワクさせるものだった。




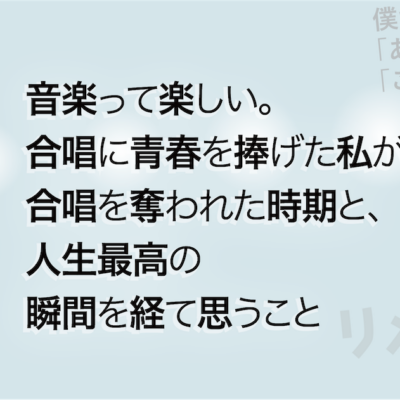


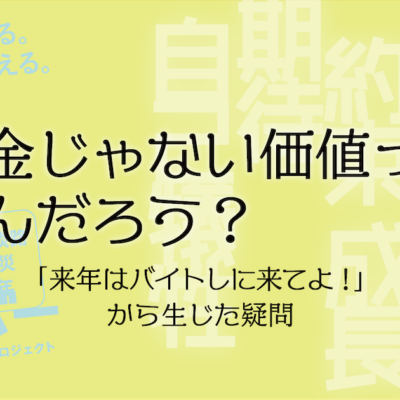


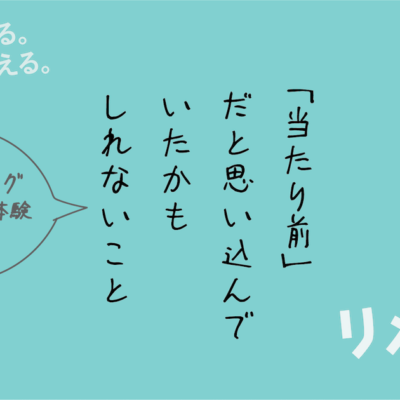


-400x400.jpg)





