「ほうしゃのう女」(生子達矢)

小学2年生の秋、一人の女の子が僕のクラスに転校してきた。彼女は折り紙がとても上手で、当時折り紙が大好きだった僕に、色々な折り方を教えてくれた。しかし、彼女がどこから来たのかは誰も知らなかった。自己紹介のとき、先生も彼女自身も、それには一切触れなかったからだ。
それから三ヶ月が過ぎ、クリスマスが近づいたある日、彼女の靴がゴミ箱に捨てられているのが見つかった。クラスでは学級会が開かれ、誰がそんなひどいことをしたのか話し合った。たしか、五時間目が終わったあと、日が沈むまで続いたと記憶している。彼女は明るく、優しい子だった。いじめられる理由なんて、僕には思い当たらなかった。
しかし、翌朝——終業式の日、彼女の机に「放射能女」という落書きがされていた。その文字を見た瞬間の衝撃を、僕は今でもはっきりと覚えている。
クラスの誰かが、落書きを見て笑った。「放射能がついとる人ってほんまに光るんかな」と、面白がるような声が上がった。「夜になったら光るんちゃう?」——悪ふざけと無邪気な残酷さが混ざった、子ども特有の笑い声が広がる。その瞬間、クラスの空気は決まった。彼女は「そういう存在」として扱われるようになった。
冬休みが明けたある朝。彼女が折った美しい折り紙が、あの落書きとともにゴミ箱に捨てられていた。その日の放課後、僕は彼女が福島から引っ越してきたのだと知った。そう——彼女は、あの原発事故のあった福島から来た子だったのだ。
彼女は全てを失ってやって来たのではなかったのだろうかと、今になってふと思う。
震災の日、彼女は家を失い、学校を失い、大切な友達や、もしかすると家族すらも失ったのかもしれない。突然奪われた日常。すべてが津波に飲み込まれ、放射能という見えない恐怖が街を覆った。避難所での日々を経て、新しい土地で、新しい生活を始めようとした——そのはずだったのではないか。
けれど、新天地で彼女を待っていたのは、新しい希望ではなく、新たな苦しみだった。
「放射能女」
そのたった四文字が、彼女のすべてを否定した。過去も、現在も、未来も。まるで、ここにいてはいけないとでも言うように。
彼女が福島から来たことを知った瞬間、僕の心に言いようのない不安が広がった。「放射能」という言葉が、子どもながらに見えない脅威のように思えたのだ。もし彼女と一緒にいることで、自分まで「汚染された」と思われたら——そんな漠然とした恐怖に駆られ、僕は少しずつ、彼女と距離を置くようになった。
彼女へのいじめは次第にエスカレートしていった。机には何度も「放射能女」と書かれ、消しても、机を取り替えても、また繰り返された。それでも僕は、何も言えなかった。もし彼女をかばえば、次は自分が標的になるかもしれない。そんな思いが、僕を黙らせた。
ある日、彼女の筆箱が開けられ、消しゴムや鉛筆が床にぶちまけられていた。それを見つけた誰かが言った。「これ、拾ったらヤバくない?」まるでそれに触れることで、自分まで「汚染」されるかのように。皆、遠巻きに見ながら、誰も拾おうとはしなかった。僕も——彼女自身でさえも。
彼女は、その場でただ立ち尽くしていた。表情はあまり覚えていない。
そして二ヶ月後、彼女はまた転校していった。理由は分からない。家の都合だったのかもしれないし、あるいは——。けれど、今になって思う。彼女を本当に苦しめたのは、あの落書きを書いた誰かだけではなかった。何もせず、ただ見ているだけだった僕もまた、加害者の一人だったのかもしれない、と。









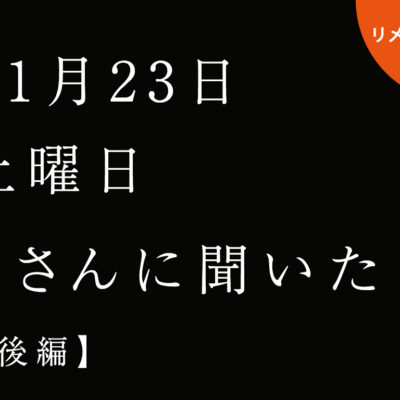



-400x400.jpg)





